厚生労働省は、介護についての理解と認識を深めるための啓発を重点的に実施する日として、「介護の日」を制定しました。
11月11日には、「いい日、いい日、毎日、あったか介護ありがとう」という思いがこめられています。
また、11月4日から11月17日までは、福祉・介護サービスの意義の理解を一層深めるための普及啓発及び、福祉人材の確保・定着を推進するための取り組みが努められています。
介護者の多くは「頑張らなければ」と強く思い、疲れてしまいがちです。
いつ終わるともわからない長い道だから・・・がんばらない介護生活で肩の力をぬいて、介護ができるといいですね。
がんばらない介護生活を実現する5つのポイントを心掛けてみましょう。
1一人で介護を背負いこまない
家族皆で介護を分担する。
「家族の会」などで、ほかの介護する人・介護を受ける人たちと悩みを話し合う。
2サ-ビスを積極的に利用する
事態が深刻になりすぎる前に公共のサービスを利用する。
介護する人は自分の時間を作る。
サービスは自分に合ったものを選ぶ。
3現状を認識し、受容する
介護を受ける人は障害と共に生きていくという現実を受け入れる。
介護する人は介護をするという現実を受け入れる。
元に戻そうとするのではなく、本人が生活しやすい方法をみつける。
4介護される側の気持ちを理解し、尊重する
介護を受ける人の何かをしようとする気持ちを大切にする。
介護を受ける人本人が幸せな気持ちになれるようにすると、介護を受ける人の負担が減る。
5出来るだけ楽な介護のやり方を考える
介護を受ける人にもできることは自分でしてもらう。
介護用品や福祉用具を上手に使いこなす。
(がんばらない介護生活を考える会より)
頑張り過ぎはストレスのもとです。
長期戦だからこそ、自分流の楽な「がんばらない」介護方法を見つけることが大事ですね。
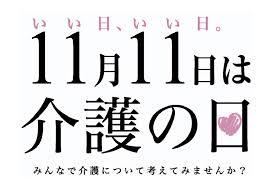
「介護では 頑張り過ぎず 自分流」
アイゼン、心の俳句・・・。

