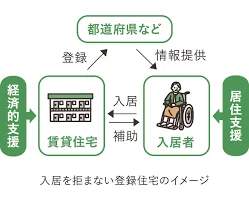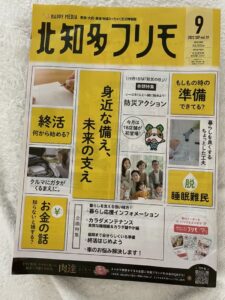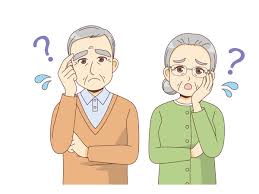認知症の人本人の意見を集め、施策の立案に生かす自治体が増えているようです。
「水道の蛇口を閉め忘れたら、もう蛇口を触らないでと言われる。同じ失敗でも、認知症でない人はそうは言われない」
「だから失敗したことを隠したくなる。認知症の人は皆そうだと思う」
認知症の人から具体的意見を聴取しよりよい暮らしと活躍をしてもらう取り組みを考えます。
第一の指針として「認知症・認知症の人への先入観の払拭」を掲げます。
認知症になると何もわからなくなる、介護が大変といった否定的なイメージを拭い去る狙いです。
認知症の人が「迷惑をかけて申し訳ない」と思わないような街づくりを!
道に迷って困っても「認知症です」と言える街づくりを!
などを望む声がでているようです。
これを受け、認知症本人や家族の声を聴く「街かどケアカフェ」などの場所の拡大を検討。
本人に聴くことは時間も手間もかかるし工夫もいりますが一緒に考えないと施策を進められません。
政府の関係閣僚会議が2019年にまとめた認知症施策推進大綱では、「認知症の人本人の視点を施策の企画・立案や評価に反映するよう努める」と明記されています。
行政と本人と一緒に施策を練り上げる姿勢が求められています。
「本人の 声を生かして 取り組みを」
アイゼン、心の俳句…。