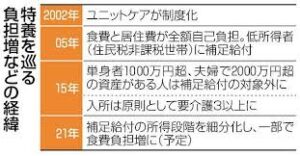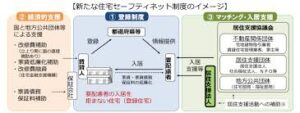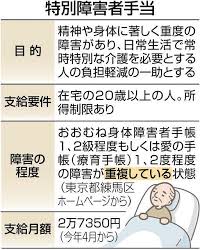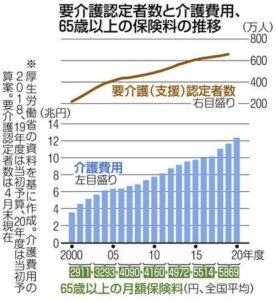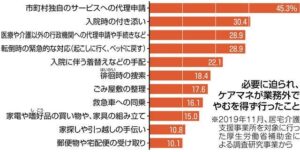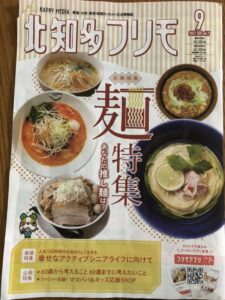大人になってからも、親との関係に葛藤を抱える人は少なくありません。
年老いた親は、かつての親とは違う存在になっているはずですが、心の中には幼い頃の親のイメージが残っています。
こうしたイメージは「内的対象」と呼ばれ、常に私たちの生活に影響を及ぼします。
内的対象が良いものであれば、親が認知症になったとしても介護を引き受けられるでしょう。
しかし、親から暴力や暴言を受けてきた人が介護に直面すると、葛藤が再燃し、大きな苦痛を伴います。
義務感だけで始めても、介護で関わる中で、過去の親子関係にまつわる感情がよみがえるからです。
では、親子関係に葛藤がある場合、どうすれば介護がうまくいくでしょうか?
まずは、親との思い出を整理してみることです。
精神分析的精神療法では、思い出などを話すことで内的対象を明確にして、そこに結びついている感情を整理していくそうです。
過去を語るうちに、親の違った側面が見えてくることがあるようです。

「思い出と ともに感情 整理する」