4月17日(土)、知多半島一部地域に中日新聞の折込広告を入れさせて頂きました。


コロナ感染防止対策として、360度カメラを設置し、お客様には非対面で作業の様子をご確認いただけます。

アイゼンでは、無料見積もりをさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さいね。


受付時間 9:00~19:00
新聞折込(4月17日)
4月17日(土)、知多半島一部地域に中日新聞の折込広告を入れさせて頂きました。


コロナ感染防止対策として、360度カメラを設置し、お客様には非対面で作業の様子をご確認いただけます。

アイゼンでは、無料見積もりをさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さいね。
先端技術を介護に活用
コロナ禍をきっかけに、オンラインの会議や飲み会がすっかり身近なものとなりました。
介護施設でも、タブレット端末などを使い、入居者と家族が顔を合わせられるようにする取り組みが広がっています。
離れて暮らしていて、あまり連絡を取る機会がなかった親類とも、すぐにつながることができます。
認知症介護で家族を悩ますのが徘徊です。家を出ていくと探すのが大変ですが、今ではGPSという位置情報を教えてくれる技術があります。
洋服に付けられる小型の装置やGPSを内蔵した靴も開発されているようです。
家族は自分のスマートフォンやパソコンなどで、認知症の人がどこにいるのかを知ることができるのです。
介護現場ではロボットの活用も始まりつつあるそうです。
その一つに、服用支援ロボットというものがあります。
設定時間になると音声で知らせて薬を出し、飲み忘れや飲み違いを防いでくれます。
さらに、人が触れると動物のような反応をし、心を安定させてくれる動物型ロボットもあるそうです。
ほかにも、先端技術を使った介護がありそうですね。
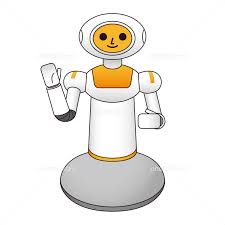
「介護にて 先端技術を 活用し」
アイゼン、心の俳句・・・。
遠距離介護
新型コロナウィルスの感染拡大で、遠く離れた故郷に住む高齢の親を介護するための帰省ができず、苦労を重ねている人も多いでしょう。
感染すると重症化する危険性が高い高齢者を預かる施設側は、十分な感染防止対策をとっていても、外部の人との接触に神経質にならざるを得ません。
今も面会の制限をしている施設は少なくないそうです。
緊急事態宣言が解除されましたが、再流行時に県境をまたぐ移動が制限される事態に備え、親の様子を画像で確かめられるオンライン環境を整えることはお勧めです。
ビデオ通話ができれば、親の顔を見て話しながら様子を確認でききます。
もし、帰省が難しくても、やれることはあります。
〇要介護認定の手続きを・・・
故郷の地域包括支援センターによる代行申請などを活用する
〇要介護状態の親の様子が心配・・・
担当ケアマネージャーと電話やメールで連絡を密にし、
必要に応じて介護サービスを調整する
〇親の様子を見守りたい・・・
電気ポットの利用や冷蔵庫、ドアの開閉を検知してメールなどに送信する「見守りサービス」を活用
(見守りカメラもあるが、設置は親の承諾を得る必要がある)
移動が緩和された、今のうちに実家に帰り、環境を整えられるといいですね。

「今のうち 通信環境 整えて」
アイゼン、心の俳句・・・。
境界をなくして
親や配偶者が認知症になったと、オープンに話せる人は多くはないものです。
家族には外部との「境界」があり、境界を通して地域や親せき、医療機関などとやりとりをします。
認知症ケアは介護者一人では困難です。
境界を解放して、外部との情報交換を円滑にする必要があります。
病気に関する情報を得るには専門家との境界、徘徊で行方が分からなくなった時に保護してもらうには地域との境界を開かなければいけません。
しかし、家族にメンタルな問題が生じると、むしろ境界が固く閉ざされてしまうことがあります。
認知症介護のことを誰にも言わずに介護者一人が抱え込み、介護疲れによる心中事件が起きてから、初めて近隣住民が知るというケースもあるようです。
「以前と様子が違うな」と感じたら、周囲が声をかけて下さい。
話し相手になるだけでも介護者のストレスは和らぎます。
介護者が自ら境界を開くのは抵抗があるかもしれません。
勇気を出して、まずは子どもや孫など家庭内の境界、次はケアマネージャーや医師ら専門家との境界、そして地域との境界を開いていきましょう。
きっとあなたの味方になってくれるはずです。

「境界を なくして心も 解放を」
アイゼン、心の俳句・・・。
介護者が倒れた時に備えて
老老介護の場合、介護者が突然亡くなることは珍しくありません。
介護は緊張を強いられることが多く、うつや不安障害など精神面の問題だけでなく、身体面にも影響が出てきます。
介護者が亡くなると、残された家族は誰が代わりに介護を担うのか、施設入所を考えるかなど、今後の介護について決める必要に迫られます。
このとき、一人に介護を任せていた家族ほど、混乱もやもやは大きくなります。
そして、盲点なのが相続の問題です。
介護者が亡くなると、その財産を分割する手続きに入りますが、それまで介護を受けてきた認知症の家族も相続の対象になりす。
認知症のメンバーがいると遺産分割協議はできませんし、認知症だからといって、相続対象から外すこともできません。
成年後見制度などの活用が必要となるため、専門家への相談など、家族が処理すべき問題は一気に増えます。
もし今、介護を担っている家族が倒れたら、どうすればいいのか?
誰が何をするのかといった役割分担と、経済的なことについて、事前に話し合って決めておきましょう。
備えをきちんとしておくことが、介護を頑張っている家族の気持ちを救うことにもつながります。

「介護者が 倒れる前に 備えよう」
アイゼン、心の俳句・・・。
介護の対応の仕方を変えてみる
排せつは、家族にとってストレスの大きな介護の一つです。
トイレの失敗が多くなると、排せつ物の後始末などが増え、精神的な負担が大きくなります。
介護する側は何とかして本人に言い聞かせようとしますが、なかなかうまくいきません。
特に、介護する人に子育て経験がある場合、子どもの「トイレトレーニング」と同じような感覚で、認知症の人に接してしまいがちです。
ですが、子どもと認知症の人は違います。
子どもは、トレーニングを重ねて身につければ、上手に排せつができるようになりますが、認知症の人は記憶障害があるため、言われたことを忘れてしまうからです。
認知症の介護では、相手の行動を変えようと思っても、難しいケースが多いです。
介護する自分自身の考え方や、対応の仕方を変えることで、うまく問題に対処できるかもしれません。

「介護者が 対応変えて 気持ち楽」
アイゼン、心の俳句・・・。
新聞折込(3月6日)
昨日3月6日(土)、知多半島一部地域に中日新聞の折込広告を入れさせて頂きました。


お問合せの中で、「大体の料金はいくらですか?」とのご質問が多いようです。
費用は、部屋の広さや作業時間によっても変動します。
また、同じ部屋の広さでも料金が異なる場合は、処分したい家財の量や種類によって料金が変動するためです。
そのため、口頭でお応えできる費用は、あくまで概算・目安となります。
より具体的な費用・料金が知りたい場合、訪問見積りをされる方がおすすめです!!
料金の決まり方は、
1荷物の量
2処分品の種類
3建物の状況
(建物の階層やエレベーターの有無、平屋かなど)
4オプションサービス
(家電の処分、家屋の解体など)
によって変わります。
自分の要望や作業して欲しい事に近い業者を選ぶ方が、作業もスムーズで費用もかからない可能性があります。
料金を安くするポイントとして
1できる範囲で事前に片付けておく
遺品整理の料金は処分する物の量が多いほど高くなります。
あらかじめ、できる範囲で処分しておくと費用をおさえられることができます。
良い業者を選ぶポイントとして
1遺品整理士が在籍しているか
2訪問見積もりに応じてくれるか
3不用品を適切に処分しているか
4対応が丁寧か
などがあげられます。
アイゼンでは、無料見積もりをさせて頂いておりますので、お気軽にお問合せ下さいね。
糖尿病患者の注意点(災害時)
糖尿病患者は、災害時の避難所でも注意が必要です。
横浜市の専門医ら糖尿病ケアチームが患者向けの災害時マニュアルを発行し、薬の準備や使い方、食事のとり方、感染症を防ぐ足や口腔ケアなどを紹介しているそうです。
足が冷たい、歩くと痛いといった人は血行が悪いと考えられます。熱さや冷たさが分かりにくいなど感覚が鈍い人は神経障害の可能性があります。
こうした人がけがをすると、傷が治りにくかったり、傷に気付きにくかったりするリスクが高いそうです。
避難所では靴下や底の厚い靴で足を保護するよう、マニュアルは勧めています。
口の中の細菌による歯周病の悪化や肺炎を避けるには口腔ケアも大事です。
水か十分でない場合に備え、すすぎが不要な液体歯磨きや洗口液、ウェットティッシュを準備しておくと便利だそうです。
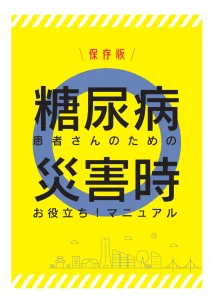
「災害時 マニュアル把握し 役立てて」
アイゼン、心の俳句・・・。
糖尿病患者の感染症について
国内で約1千万人がかかっているとされる糖尿病。
広がり続ける新型コロナウィルスを巡っては、感染すると重症化しやすい基礎疾患の一つに挙げられています。
専門家によると、そもそも糖尿病の患者は新型コロナに限らず、様々な感染症にかかりやすいそうです。
日ごろから感染予防を心掛けるとともに、かかった場合の対処法を知っておくことも大切です。
新型コロナを含め感染症を防ぐには、手洗いや人混みを避けるといった基本対策の徹底に加え、神経障害などの進行を防ぐため、血糖値を良い状態に保つことが大事だそうです。
初期は自覚症状もないため、健康診断で指摘されても放置する人が少なくないそうです。
新型コロナが広がる今、自分は治療の必要があるかなどをきちんと把握しなければなりません。

「予防には 体調変化の 確認を」
アイゼン、心の俳句・・・。
問題に応じた専門家
両親や配偶者が亡くなった時などに、突然始まる相続の手続き。
めったにない上に煩雑とくれば、専門家に任せたいと考える人も多いでしょう。
ただ、相続といっても中身は様々です。
手数料だけでなく、依頼する専門家の実績や得意分野なども確認し、円滑、円満な相続につなげたいものです。
相続の手続きは、自分でもできるケースと、専門家に依頼した方が無難なケースがあります。
例えば、不動産が自宅だけで、登記を行う法務局へ2~3回通う余裕があれば、自分で手続きすることも可能なようです。
金融機関の名義変更なども口座数が限られていて戸籍謄本や遺産分割協議書など必要書類をそろえれば自力でできるそうです。
ただ、農地などの不動産が複数ある場合や、相続税の課税対象者など手続きが煩雑な場合は、司法書士や税理士などの有資格者のほか、有資格者らをつないで調整する行政書士やFP、不動産、金融関係者ら専門家への依頼を検討することをお勧めします。
専門家にはそれぞれ得意分野があります。
手数料が心配な場合は、複数の専門家から相見積もりをとりましょう。
節税だけでなく、円満かつ円滑な相続にしたいものです。
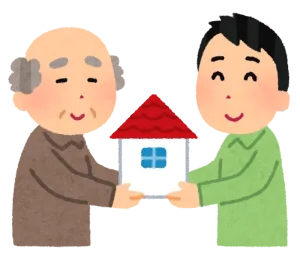
「問題に 応じた専門 相談を」
アイゼン、心の俳句・・・。
自筆の遺言に保管制度
前回のブログ(2月7日)「相続を話し合うために」で遺言者が自筆で作成する「自筆証書遺言」について少しふれました。
この証書を、法務局で保管する制度も始まっています。
自筆証書遺言とは?
財産目録など以外は本人の手書きで作ります。
証人がいらず、費用もかからない手軽さがメリット。
ただ、自宅での保管には紛失や他人による改ざん、誤って破棄してしまうことなどへの懸念や、死亡後に発見されなかったり、民法で定められた書式と合致しなかったりして無効になるケースもあります。
保管制度はこうしたトラブルの回避に役立ちます。
利用希望者は管轄の法務局に予約し、遺言書を持って出向きます。
遺言書保管官が書式や署名、押印、日付などを確認。
原本は法務局で保管し、画像データも残します。
相続人らは本人の死後、法務局に問い合わせれば、遺言書の存在を確認できます。
ただ、遺言を残す本人が法務局で申請する必要があり、寝たきりや遠方の人は使いにくいです。
また、保管官は内容や作成者の判断能力までは確認せず、有効性を担保するものではありません。有効性を回避したいなら、数万円の費用はかかりますが、本人の意思を確認してまとめる公正証書遺言を準備するのも手です。
これは、証人二人以上の立ち会いのもと、公証人が遺言書を作成し、公正役場で保管します。
偽造などの恐れがなく、公証人が法律に照らして内容を確認するため、後日無効になる心配もありません。
制度を知り、円滑な相続にお役立てください。

「制度知り 相続トラブル 回避する」
アイゼン、心の俳句・・・。
相続を話し合うために
相続トラブルの防止には、親など本人が、元気なうちに自分の死後について考え、家族のために遺言などを準備しておくことが大切です。
とはいえ、本人が何もせず、家族ら周囲がやきもきするケースも多いものです。
周囲からの切り出し方を間違えると、かえって話がこじれてしまう場合もあります。
本人の機嫌を損ねずに話を進めるコツが新聞に載っていましたのでご紹介します。
キーワードは「介護」だそう。
いきなり相続を話題にするよりもハードルが低いようです。
実際、相続でもめる原因の一つが介護の負担に基づくものです。
相続を機に、互いにため込んだ不満が噴出することがあるからです。
それから、「公正証書」での遺言の作成です。
ただ、「遺言=遺書=死」という連想は根強く、警戒して避けたりする親もいます。
ですので、「公正証書を作って」と言い換えるといいそうです。
公正証書遺言の作成にあたっては、法律の専門家に依頼したり、費用などの負担もあります。
それに対し、費用のかからない自筆証書遺言が昨年1月から、財産目録をパソコンで作ったり、通帳などをコピーして添付したりしても良いことになり、負担が軽減されます。
※↑このお話は、次回に続きます。
後に遺言の有効性を争うトラブルなどを防ぐため、話し合いや手続きにはできれば子どもら関係者全員が参加するのが望ましいそうです。
忘れてはいけないのは親を尊重すること。
それが「争族」を防ぐことにもつながるそうです。
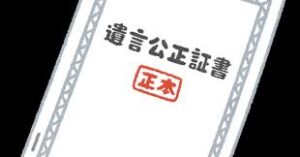
「遺言は 介護を糸口 作成を」
アイゼン、心の俳句・・・。
![]() LINE見積り方法
LINE見積り方法