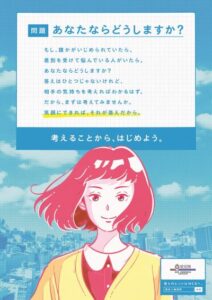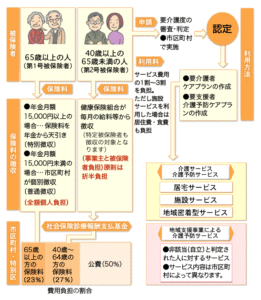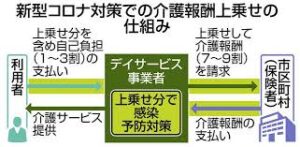あっという間に12月半ばです。
昨年の今頃、まさかこんな年になるとは思いませんでした。
今の状況だと、来年もしばらくこのような状況が続くと予想されます。
現代社会は、一人でもある程度充実した暮らしができる便利な社会です。
ただ、便利だけでは得られないのが、人との交流によって得られるものです。
誰かとつながっている感覚とか、いざという時に気が付いてもらえる安心感などです。
コロナ禍でのステイホームは、現役世代にとって、老後生活の予行演習のようなものになった気がします。
この先コロナ禍が収まった時、もっと楽しい日々がきっとやってくるはずです。
希望を持って新年を迎えたいものですね。
さて、年末年始のお休みを、下記の通り頂きます。
12月28日(月)~1月5日(火)
よろしくお願い申し上げます。
また、休み中でも電話やメールでの問い合わせをお受けしております。
返事が遅くなる場合もございますが、お気軽にご相談下さいませ。