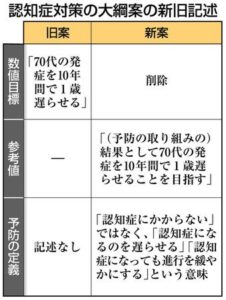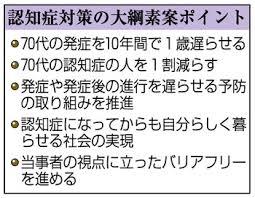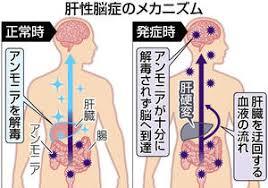昨日、九州北部と四国、中国、近畿の梅雨入りが発表されました。
平年より大幅に遅れ、1951年の統計開始以降、最も遅い梅雨入りだそうです。
そんな梅雨のこの時期に、肩こりや頭痛、だるさといった体の不調を感じる方が多くいるようです。
それは、「次々と通過する低気圧の影響」を受けるからです!
そこで、新聞に載っていた、ストレッチなどの対処法をご紹介します。
梅雨時期に起きる、肩こりの改善方法
首タオルストレッチ
①タオルの両端を持ち、耳の下にかける
↓
②斜め上を向き、タオルを引っ張りながら首でタオルを押して30秒
↓
③舌を向いて、同様に30秒
耳ストレッチ
①耳たぶの少し上を水平方向に引っ張り、5~10秒したら離す。
これを数回繰り返す。
みみを上下に動かすのも効果的!
②耳たぶの後ろの骨のくぼみ(顎関節)を少し痛くなる程度に強めに30秒押す。
離した時に軽くなっていれば大丈夫!

ストレッチで血行を良くし、少しでも体調良く梅雨を乗り越えられるといいですね!