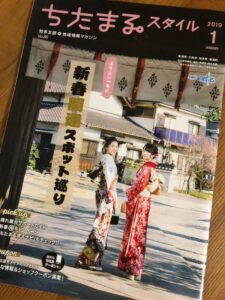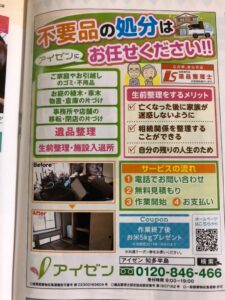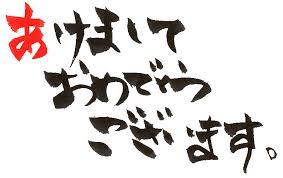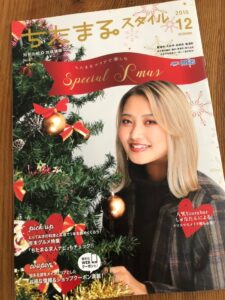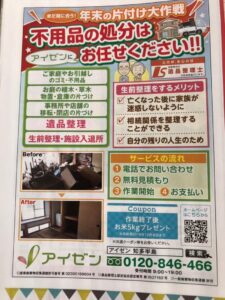1月13日のブログ(故人の品を再び世へ)の続きのお話です。
年間130万人を超える人が亡くなる多死社会となった日本。
1軒家が残されると膨大な遺品が出て、その処分に困る遺族が増え続けています。
ここ数年、そうした遺品を再生させようという動きが加速しています。
昨年NHKで放送されていた、「広がる遺品再生ビジネス」日本製品が「中古でも欲しい」というアジアのニーズを受けて、フィリピンでオークションをおこなっている会社があるそうです。
経済成長を続けているフィリピンでは、より豊かな暮らしを求める市民の間で、日本人が使ってきた品々が人気を集めています。
特に和ダンスは気密性があり、なおかつスムーズに動くということで人気です。
食器や調理器具なども、人気のようです。
中古品の方が人気な理由に、日本人が大切に使ってきた遺品なら、丈夫で質がいいと、むしろ付加価値になっています。
メード・イン・ジャパンではなく、ユーズド・イン・ジャパンですね。
遺品になる前に「形見分け」をすることで、「大切なものを必要とされる場所で再生」させようと考えたようです。
遺品を引き受ける、継承する人たちが少なくなっているので、解体されてゴミとして処分されるより、世界のどこかに使ってくれる人がいるなら、とても素敵なことですよね。

「海渡り 大切な遺品 他の手に」