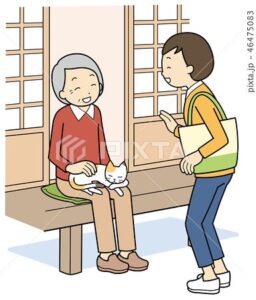相続トラブルの防止には、親など本人が、元気なうちに自分の死後について考え、家族のために遺言などを準備しておくことが大切です。
とはいえ、本人が何もせず、家族ら周囲がやきもきするケースも多いものです。
周囲からの切り出し方を間違えると、かえって話がこじれてしまう場合もあります。
本人の機嫌を損ねずに話を進めるコツが新聞に載っていましたのでご紹介します。
キーワードは「介護」だそう。
いきなり相続を話題にするよりもハードルが低いようです。
実際、相続でもめる原因の一つが介護の負担に基づくものです。
相続を機に、互いにため込んだ不満が噴出することがあるからです。
それから、「公正証書」での遺言の作成です。
ただ、「遺言=遺書=死」という連想は根強く、警戒して避けたりする親もいます。
ですので、「公正証書を作って」と言い換えるといいそうです。
公正証書遺言の作成にあたっては、法律の専門家に依頼したり、費用などの負担もあります。
それに対し、費用のかからない自筆証書遺言が昨年1月から、財産目録をパソコンで作ったり、通帳などをコピーして添付したりしても良いことになり、負担が軽減されます。
※↑このお話は、次回に続きます。
後に遺言の有効性を争うトラブルなどを防ぐため、話し合いや手続きにはできれば子どもら関係者全員が参加するのが望ましいそうです。
忘れてはいけないのは親を尊重すること。
それが「争族」を防ぐことにもつながるそうです。
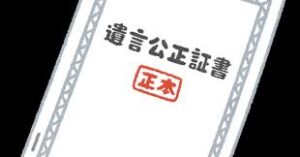
「遺言は 介護を糸口 作成を」
アイゼン、心の俳句・・・。